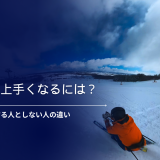この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
また、スキーダイエット.jpは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

hide
元アルペンスキー選手、1級所持
スキー上達法や最新のアルペンスキー速報、個人的なダイエット、体脂肪率、食べた後の筋肉量の変化をほぼ毎日記録してます。トップページに情報をまとめてるのでブックマークしておくか、「スキーダイエット.jp」と検索すると便利です。また、個人的なプロフィールやスキーの戦績、資格などの実績の証拠写真は記事下のWebsiteリンク先にあります。

スキーは冬のスポーツと思われがちですが、実はハードな練習は夏の方です。主にアルペンスキー選手がどんな夏のトレーニングをしてるか紹介していきます。
「ダイエット」の本当の意味は「痩せる」ではないです。健康的な生活習慣全般を意味します。ここではスキーに必要なレベル別の体作りと生活、食事について説明してます。
まず結論から言いますが、世界中で様々な研究があり、わかったことは
スキーが上手い選手、速い選手ほど体力がある(筋力など)
ということがわかってます。
いろんな研究があり、各国、チームごとでも全くスキーのトレーニングメニューが違います。
私もアルペンナショナルスキーチームメンバーがいるチームと夏の合同合宿をやった経験があるので、どのくらい私と体力の差があるのか、彼らの劣ってる部分、ナショナルチームに送り出すコーチ別の練習内容などを思います。
なぜスキーヤーは夏で差がつくのか?

まずスキーのレベルと体力がなぜ関係するのかというと、上記のSNS投稿の通りとなります。
アルペンスキー選手にしろ、基礎スキーヤーにしろ1回の滑走時間は大体1分から2分が平均ではないかと思います。
具体的に種目別に並べると
- ダウンヒル(滑降):2分前後
- スーパー大回転:1分30秒
- 大回転:1分から1分30秒(1分40秒というレースもありました。ニセコアンヌプリの最終戦でした)
- 回転:1分前後(ターン数60から70)
- 技術選(基礎スキー):30秒から1分
だいたいこんな感じです。
この時間帯に
- 何回もターンをし
- スピードも求められ
- スピードのある中で正確な操作が求められ
- ゴールするまでに太ももの筋力が持つようにする(スクワットに近い上下運動を繰り返すため)
です。
上下運動をなぜスキーヤーがするのかは下記の動画で解説してます。
上記の比較動画を見れば一目瞭然ですが、上下の運動を入れるとスキーはどんどんスピードアップします。
これはアルペンスキーの基本中の基本の話で、これができないとタイムが出ません。技術選のような中腰から中腰は見栄えは良いかもしれませんが、アルペンでは通用しない滑りです。
もちろん、頭をあまり動かさないで無駄な動きは上手くなるほど減っていきますが、基本可能な限り上下の動きを使わないとパワーが生まれないのがアルペンスキー競技です。
上下に動くということはスクワットのような動きになるので、下半身強化していないスキーヤーは
- 練習の途中で足がパンパンになり、滑走中に足をつる。最悪、転倒し怪我をする。
- 足が限界になるとそれ以上練習ができなくなる(練習の質を落とす)
- 試合でゴールまで足がもたない
といった現象が必ず起きます。
なので、スキー選手のほとんどは
- 持久力
- 筋持久力
- 瞬発力(筋力)
の3大トレーニングを必ず行っており、私自身もアラフィフですが、今も1日1時間から2時間の陸上トレーニングをやってます。
*トレーニングメニューや食事は下記で解説中
アルペンスキーを例に出すと、諸説ありますが今の時代は10%から12%くらいが理想ではないかと思います。
ボディビルなどの動画を見ると一桁になるとパワーが減るといった研究内容を紹介するところもあるので、人間の生理的にも10%は残しておかないと踏ん張りが効かないですし、ウエイトトレーニングの質も落ちる可能性があるかと思います。
また、筋力に関しても諸説ありますが、アルペンスキー選手は2つのパターンがあり
- 湯浅直樹さんのような1日16キロ走るアルペンスキー選手もいれば(ずっとやっていたかは不明。北海道のローカル放送で紹介されてました。)
- アルベルトトンバやティモン・ハウガンなどパワー型に仕上げて落下速度と瞬発力で勝負する
2タイプに分かれます。
例えるなら湯浅直樹さんはサッカー選手、欧米のパワー系スキー選手はラグビー選手に近いかもしれません。
サッカー選手の体脂肪率は7%前後と言われており、ラグビー選手はパワーも必要なので14%の体脂肪率と言われてます。(サッカー日本代表と戦った当時のベルギー代表はみんなパワー系に見えますが・・・あそこは特殊かも。)
しかし、アルペンスキー競技に限って言えば
- 失敗を少なくする丸いターン弧を描く滑りにするために「動きがしなやか」「柔らかい」滑りにするタイプ(丸いと言っても鋭角に近いターン弧)
- 多少失敗しても良いので、パワーと落下速度でタイムを出すタイプ(ハウガンは板のトップがよく浮きますよね。あれはパワーを最大化するために、センターの位置(重心)をギリギリのところに調整してるからです。トップが浮いてもパワーで抑えるフィジカルが彼にはあるので速いのです。)
に分かれるので、どちらの滑りに自分の体を合わせていくかでもトレーニングが変わってくるはずです。
ティモン・ハウガンの強さを今色々見てるのですが、
①重心が少し後ろ気味に調整
②でも後傾姿勢にならないギリギリのラインでリスクを負って
③ターン後半の加速重視 というのが今季の印象です。
映像はこちら
あと最大の違いは5年前のロシニョール時代と見比べると
明らかに肉体改造してきた ことです。 体重?が明らかに大きく変化してます。重さと瞬発力が増してるのでターン後半が加速し、さらに深い内傾角でも内倒せず、体幹やバランスが向上してる影響もあるでしょう。
*ロシニョール時代のハウガンの映像はこちら
例えば皆川賢太郎(173cm)さんは身長が日本人選手の中でも低めですが、体重が89キロあったことは有名です。(湯浅直樹さんは177cm、佐々木明選手、木村公宣さん、岡部哲也さんはみなさん180cm以上)
164cmのポポフは2025年に男子スラロームで初優勝してますが、やはり筋肉ムキムキ系の体で、筋肉で体重を増やして落下速度と瞬発力でカバーしてる部分があります。
フィジカルだけでなく技術の個人差があるので一概には言えません。ただ、単純に身長が高い選手ほど同じ筋トレでも全体の筋肉量の面積も広いので、結果体重も身長が低い選手より落下速度で有利に立ちやすいと考えます。特にアルペンW杯は昔から180cm以上の選手、または筋肉量と筋力がある選手が数多く活躍してます。
なので脂肪で体重を増やすのではなく、
「体脂肪率を可能な限り低くしながら、筋肉量と筋力の両方を上げていく」
という至難の業をやらないと、そもそもタイムの面で不利になるので体力強化がスキーでは必須なのです。
筋肉量と筋力は違います。ある程度比例しますが、筋繊維が細いアスリートでも筋力のある選手は重いものを持ち上げることができます。パワーリフティング選手とかレスリングの選手が参考になります。湯浅直樹さんは筋力があるタイプではないかと思います。全国中学の高跳びで3位という記録もあるので、関節の動きなど繊細な感覚があり、力の伝え方が非常に上手い方だと思います。
これは実際に筋トレするとわかりますが、なかなか技術的にも難しく、食事管理が非常に重要になります。
ただパワーを上げるだけなら肉体改造をした大谷翔平選手のように
- 脂質の少ない食べ物を食いまくって
- ひたすら限界までウエイトトレーニング(多少脂肪はつく)
- 持久系運動をやらない(怪我のリハビリ期間で体が大きくなったのは有名)
をすれば体自体は誰でも大きくなります。
私も1ヶ月で筋肉量を4キロ増やしたことがあります。(2024年2月から3月。1級検定でターン後半の加速が欲しかったために)
しかし、落下速度は上がっても筋力が上がったわけではありません。
急激な体重増加で1級大回りとか小回りが速くなっても、不整地で膝を痛めそうになったので体脂肪を一桁まで減らすため、半年かけて昨年ダイエットをしたのです。
筋肉量は体重77キロに対し約62キロ(体脂肪16.7%)ありましたが、この記事を書いてる現在は体脂肪10%前後で体重67キロ(筋肉量57キロ)まで下がりましたが、筋力は変わってません。
むしろ前より重いものをより多くのセット数で持ち上げられるようになってます。(ウエイトのMAX想定はしてません。筋持久力が上がったと言った方が正解でしょう。)
スキーはパワーを残しつつも、動きが鈍くならない体脂肪率にするのがベスト
と私は考えます。
よくある肉体改造の失敗例がプロ野球でたまに見れますが、
「パワーが上がっても打てなくなるバッター」
がいます。
イチローさんはウエイトトレーニングに懐疑的なのはバットの感覚がズレるからだそうです。(昔はバリバリウエイトやってたそうです。結果スイングスピードが落ちたとテレビで語ってます。)
イチローさんとダルビッシュ選手の意見が正反対で昔話題になりましたが、スポーツに関しては
「結果が良くなれば正解」
なのです。
ダルビッシュ選手は「メジャーではパワーが絶対必要」と語ってました。ピッチャーとバッターでもトレーニングはかなり変わるはずです。
野球で言えばヒット量産型バッターとホームラン量産型では体型がまるで違うのがわかるかと思います。
スキーも同じで、パワー型とコンスタントに上位に来る体型(どんなポールセットでも成績が出る)では体型が異なるのではないかと私は考えます。
- 深回り:筋力・瞬発力・筋持久力のあるスキー選手が有利
- 浅回り:直線的なラインの動きなので、体重の重いスキー選手がとにかく有力(体重が重いと横移動の際、雪面からの反発が強すぎてスキーのトップが浮いたり、重い分横移動であらゆる動きで重くなるので疲れるはず。ハウガンが24−25シーズン、かなり板のトップが浮きましたよね。オデルマットも2024年夏に3キロだったか5キロ増量してから、高速系は伸びても明かに24-25シーズンのGSで勝てなくなりました。(GSリザルトはこちら)
もちろん滑りのセンスも大きく関係するのですが、結局体を動かすことには変わりありません。
自分はどんなターン弧が得意で、どんなタイプの滑りが1番成績が良くなるのか?
ここが1番大事です。
また、ポールセットの傾向がオリンピックまでの4年間で変わることが近年多くなりました。なので、ポールセットの傾向によってフィジカル数値を変化させる必要も今のアルペンスキー選手は必須と言えます。
なので、追求する滑りでトレーニングメニューも変わってきます。(高速系と技術系選手でも体型違います)
チームでやる練習メニューは全体メニューになるので自主トレなどで調整するしかないのですが、可能な限り自分なりにカスタマイズする必要があります。
イチローさんも6、7年失敗を続けたと語ってますから、できるだけ早くに自分に合ったトレーニングを見つける必要があるのです。
これはスキーヤー自身の仕事であり、コーチのやることではないのです。
スキーに必要なトレーニングメニューとは?
先ほども紹介しましたが、スキーは
- 持久力(血流を良くしてシーズン通して疲労を少なくする、スタミナをつける)
- 筋持久力(1分から2分間全力で動かせる筋肉を作る、心肺機能を上げる)
- 瞬発力(パワーを底上げし、全体の筋肉を強くする。瞬発力を上げる)
の3つが重要と書きました。
では、ナショナルチームなどトップレベルの練習はどのようなものなのか?
それは次の通りです。(随時加筆していきます。このページにスキーの細かいトレーニングを紹介していきます。)